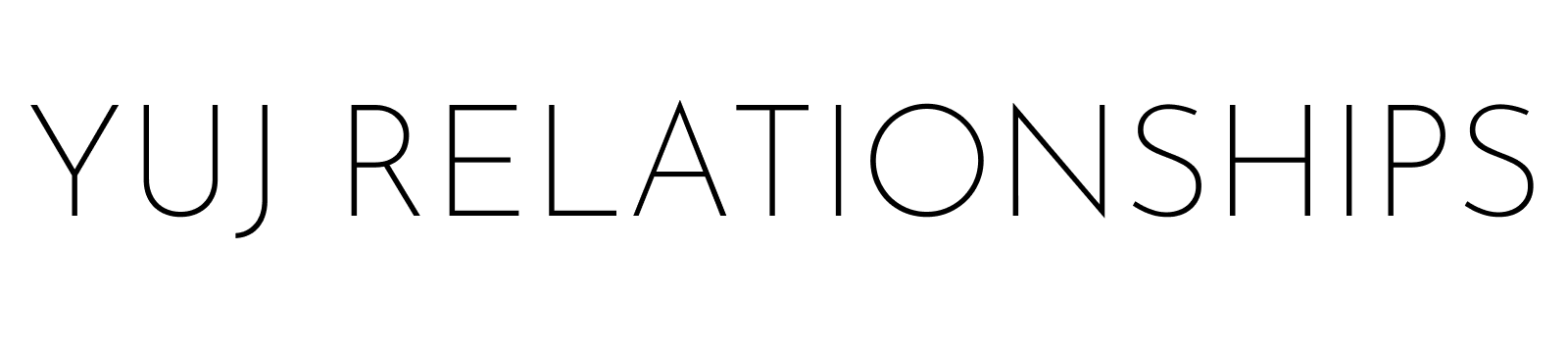アーユルヴェーダ式。梅雨を快適に過ごす方法とは?

毎年梅雨が訪れると、なんだかからだが重くて心もどんよりしてしまう…
そして頭痛やむくみなど、日々の生活がしんどくなってしまうこともありませんか?
そこでこの記事では梅雨に不調が起きるメカニズムから、アーユルヴェーダ式解消方法までご紹介します。
梅雨に不調が起きるメカニズムとは?
なぜ梅雨は不調が起きやすいのでしょうか。
その原因は気圧によるものが多いといわれています。
梅雨は気圧が下がることで交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、自律神経が乱れてしまうのです。
気圧が下がることで交感神経が刺激されることで血管が収縮して血流が悪くなり、むくみや頭痛を引き起こします。
また、雨による湿気も大きな要因のひとつです。
空気中の湿気がからだに入り込み、体内の水分が必要以上に増えることも、からだに悪影響を与えます。
アーユルヴェーダと梅雨の関係
アーユルヴェーダでは、1年で最も日照時間が長い夏至の頃を、人間の力(体力・消化力・精神力)が弱まると考えています。
確かに梅雨時は心身共にどんよりして、気力が奪われがちですね。
それは、体内のドーシャに乱れが起きているからです。
ドーシャは増え過ぎることによって、からだに様々な影響を及ぼします。
また、どのドーシャが増えるかによって症状にも違いがあります。
ここからはドーシャ別症状をお伝えしますので、梅雨に不調が起きた際はどのドーシャが増えすぎているのか、照らし合わせてみてくださいね!
カパによる影響
雨の影響による湿気で体内のカパが増えると以下の症状が引き起こされます。
・冷え
・むくみ
・からだの重さ
・だるさ
・咳
・鼻詰まり
・皮膚のかゆみ
ピッタによる影響
梅雨の後半は湿気に加え気温の暑さも加わりピッタが増えると、以下の症状が引き起こされます。
・頭痛
・イライラ
・怒りっぽさ
ヴァータによる影響
台風などの発生による気圧の変化や強風によりヴァータが増えると、以下の症状が引き起こされます。
・関節の違和感
・からだの痛み
・肩こり
・頭痛
アーユルヴェーダで叶える梅雨の快適な過ごし方

ここからは梅雨に揺らぎがちなからだを整えるための、アーユルヴェーダ的過ごし方をご紹介します。
生活習慣
日々の中で手軽に取り入れられる習慣をお伝えします。
・ヨガなど軽めの運動
・ウォーキング
・オイルマッサージ
・湯船に浸かる
血行不良が起きがちな梅雨時期は、軽めの運動を行い血流を良くしましょう。
ただし、1年の中で一番体力が弱まっている時期のため、ヨガなど軽めの運動が良いですね。
オイルマッサージはリラックス効果や、溜まった水分を排出する効果があります。
そして、気温差の激しい梅雨時期は、いつの間にかからだが冷えていることもありますので、なるべく湯船に浸かるようにしましょう。
食習慣
梅雨時期はからだの中からケアすることも大切です。
そこで、積極的に取り入れたい食習慣をご紹介します。
・白湯を飲む
・香味食材を多く摂る(生姜、ミョウガ、大葉など…)
・温かく調理されたもの
・消化に良いもの
梅雨時期は消化力が落ちますので、白湯で胃腸を活性化し、消化に負担がかからない食習慣を心がけましょう。
食欲がわかない時は、香味食材を取り入れると食欲増進に繋がります。
揚げ物や中華料理など油を多く使う食事は消化に負担がかかるので、なるべく避けた方が良いでしょう。
まとめ

梅雨がやってくるとなんだかスッキリしない日々が続く方も多いのでは。
この記事では、アーユルヴェーダを通して梅雨における不快症状の解消法をお伝えしてきました。
日々の生活で気軽に取り入れられるものばかりですので、ぜひ今年の梅雨は心身共にスッキリを過ごしましょう!